| 11/30 | |
沼津でウナギを堪能。 |
こんばんは。今日もとても良いお天気の関東地方でしたが、その分乾燥もひどくなってきましたね。
本日野暮用で、沼津まで車を飛ばして来ましたが、こんな時節なので現地滞在一時間足らずで戻って来ましたよ😃

新幹線から見慣れた輪郭とは、ちょっと違う角度からの富士山。山頂と中腹にたなびく雲がとても素敵な、絵に描いたようなバランスで撮れました。

知人とどうしても会う必要があって出向いたのですが、沼津は富士山の伏流水のお陰で泥臭さが抜け、美味しいウナギで有名なのだそうです。玄関で大きなウナギ看板が迎えてくれる、こちらは専門店の京丸さん。

水槽の中から、稚魚たちが迎えてくれます。昨年まで不漁でしたが、今年はだいぶ稚魚が戻って来たと聞きましたよね😊

ご馳走していただいたので、値段知らないのですが、都心と比べたら3/4位らしいです。豪華でしょう😁 身はもちろんふっくら、たれは少し甘めながらさらっとしていて、あっという間に完食です。

今回は運転していたから飲んでませんが、次がもしあったらこの静岡ビールと合わせてみたいです!

うまきをお土産にしてきたので、夕飯も贅沢にいただきました🥰
ごちそうさまでした🎵
本日野暮用で、沼津まで車を飛ばして来ましたが、こんな時節なので現地滞在一時間足らずで戻って来ましたよ😃

新幹線から見慣れた輪郭とは、ちょっと違う角度からの富士山。山頂と中腹にたなびく雲がとても素敵な、絵に描いたようなバランスで撮れました。

知人とどうしても会う必要があって出向いたのですが、沼津は富士山の伏流水のお陰で泥臭さが抜け、美味しいウナギで有名なのだそうです。玄関で大きなウナギ看板が迎えてくれる、こちらは専門店の京丸さん。

水槽の中から、稚魚たちが迎えてくれます。昨年まで不漁でしたが、今年はだいぶ稚魚が戻って来たと聞きましたよね😊

ご馳走していただいたので、値段知らないのですが、都心と比べたら3/4位らしいです。豪華でしょう😁 身はもちろんふっくら、たれは少し甘めながらさらっとしていて、あっという間に完食です。

今回は運転していたから飲んでませんが、次がもしあったらこの静岡ビールと合わせてみたいです!

うまきをお土産にしてきたので、夕飯も贅沢にいただきました🥰
ごちそうさまでした🎵
| 11/29 | |
新幹線の定番お供。 |
こんにちは。11月も後一日を残すのみ。このところ、来週の単位試験準備に集中していたので、いつの間にか11月が終わってしまいます。12月もあっという間に、終わってしまいそうですね😑
さて、私は学校が京都なので、ご承知のとおり時々移動してますが、最近よく新幹線に乗る前に買っているのがこれです。

豆狸の稲荷寿司、五個入パックです。豆狸は、大阪のお店ですが、品川駅にも売店があって、しかも品川駅限定の稲荷寿司まであるんです。京都でヘビーな食事を予定している時は、つなぎにちょうど良い量なんです。

ご覧の通り、五個がそれぞれ違う種類なんです。我が家から東海道新幹線に乗るには、新横浜駅からが一番合理的なのですが、このお店が品川駅にしかないので、なるべく都心での用事を組み合わせて、品川から乗るように工夫します。

ここから三枚の写真は、別の日のものですが、五種のなかでも色の黒っぽいの、気になるでしょう? と言うことで、断面の写真です。黒い理由は、黒砂糖を使っているから。普通の稲荷寿司より、黒糖のこくがあって、じわっとした風味です。

これちらが、品川駅限定商品のあさりいなりになります。といっても、見た目では五目いなりと、あまり見分けがつきませんが。。。あさりの噛みごたえと、出汁がとっても美味しいので、ヘビロテしてます🤭

それから、とっておきの変わりダネがこちら。こんにゃくいなり🤔です。ご覧のとおり、外側が油揚でなくてこんにゃくです😆 カロリーが1/3位なのと、もの珍しさでとてもよく売れているようです。
さて、私は学校が京都なので、ご承知のとおり時々移動してますが、最近よく新幹線に乗る前に買っているのがこれです。

豆狸の稲荷寿司、五個入パックです。豆狸は、大阪のお店ですが、品川駅にも売店があって、しかも品川駅限定の稲荷寿司まであるんです。京都でヘビーな食事を予定している時は、つなぎにちょうど良い量なんです。

ご覧の通り、五個がそれぞれ違う種類なんです。我が家から東海道新幹線に乗るには、新横浜駅からが一番合理的なのですが、このお店が品川駅にしかないので、なるべく都心での用事を組み合わせて、品川から乗るように工夫します。

ここから三枚の写真は、別の日のものですが、五種のなかでも色の黒っぽいの、気になるでしょう? と言うことで、断面の写真です。黒い理由は、黒砂糖を使っているから。普通の稲荷寿司より、黒糖のこくがあって、じわっとした風味です。

これちらが、品川駅限定商品のあさりいなりになります。といっても、見た目では五目いなりと、あまり見分けがつきませんが。。。あさりの噛みごたえと、出汁がとっても美味しいので、ヘビロテしてます🤭

それから、とっておきの変わりダネがこちら。こんにゃくいなり🤔です。ご覧のとおり、外側が油揚でなくてこんにゃくです😆 カロリーが1/3位なのと、もの珍しさでとてもよく売れているようです。
| 11/28 | |
台湾風豆乳豆腐と焼き肉まん。 |
こんばんは。本日はとても素敵に晴れて、気持ちの良い東京地方でした。
記事の方は、少し以前に、いつもの発酵調味料ワークショップで習ってきた軽食です。

参加者数は通常の半分に押さえているものの、ワークショップの時間をなるべく短くするため、席には材料がもう切って用意されています。ありがたいけれど、少し気が抜ける感じも。。。

この日、一番肝心の材料はこの二つ、無調整の豆乳と醤油こうじ。まず、どんぶりに醤油こうじ、黒酢、塩抜きしたザーサイのみじん切りを合わせ、スタンバイさせます。

次に鍋で豆乳を沸騰しない程度まで温め、先ほど調味料をいれたどんぶりに静かに注ぎいれます。当然最初は液体なのですが、置いておくと黒酢の酸凝固作用で、茶碗蒸しのように半熟豆腐になります。

固まり始めたら、好みのトッピングをどんどん載せていきます。この日は、干しエビ・ナッツ・ネギなどでしたが、仕上げにラー油をふるのが味の決め手。プラス色合いの決め手にもなりますね。

もう一品は、両手を使うので途中の写真がないですが、黒胡椒の効いた焼き肉まん、胡椒餅です。生地は時間がかかるので、既に発酵してあって、自分でやったのはこれを伸ばして肉餡とネギを包んだだけ😁 オーブン210℃で20分焼きます。

豆乳は10分弱で、丁度よくフルフルに。朝食にもピッタリの一品です。焼き肉まんは、思っていた以上にきれいに焼き上がったので、喜んで噛ってしまってからの写真になりました😁 個人的には黒胡椒を利かすより、生姜利かすのが好きかな。
トッピングによって、いくらでも味変できるし簡単なので、半熟豆腐はヘビロテしそうです。
記事の方は、少し以前に、いつもの発酵調味料ワークショップで習ってきた軽食です。

参加者数は通常の半分に押さえているものの、ワークショップの時間をなるべく短くするため、席には材料がもう切って用意されています。ありがたいけれど、少し気が抜ける感じも。。。

この日、一番肝心の材料はこの二つ、無調整の豆乳と醤油こうじ。まず、どんぶりに醤油こうじ、黒酢、塩抜きしたザーサイのみじん切りを合わせ、スタンバイさせます。

次に鍋で豆乳を沸騰しない程度まで温め、先ほど調味料をいれたどんぶりに静かに注ぎいれます。当然最初は液体なのですが、置いておくと黒酢の酸凝固作用で、茶碗蒸しのように半熟豆腐になります。

固まり始めたら、好みのトッピングをどんどん載せていきます。この日は、干しエビ・ナッツ・ネギなどでしたが、仕上げにラー油をふるのが味の決め手。プラス色合いの決め手にもなりますね。

もう一品は、両手を使うので途中の写真がないですが、黒胡椒の効いた焼き肉まん、胡椒餅です。生地は時間がかかるので、既に発酵してあって、自分でやったのはこれを伸ばして肉餡とネギを包んだだけ😁 オーブン210℃で20分焼きます。

豆乳は10分弱で、丁度よくフルフルに。朝食にもピッタリの一品です。焼き肉まんは、思っていた以上にきれいに焼き上がったので、喜んで噛ってしまってからの写真になりました😁 個人的には黒胡椒を利かすより、生姜利かすのが好きかな。
トッピングによって、いくらでも味変できるし簡単なので、半熟豆腐はヘビロテしそうです。
| 11/27 | |
また、ミニ野菜がたくさん届いた😊 |
こんばんは。なんか、急にコロナ重症患者数が増えましたね。東京は不要不急の外出を控えて、というメッセージがでてますが、何をどうしたら良いか現実的にはわからないです。。。
さて、昨晩はまた、糠漬け用のミニ野菜が、いっぱい届きましたよ。きれいでかわいいです😃

今年の気候は根菜類に適しているそうで、収穫は上々だそうです。9種類も入ってきた中味は、このとおりとても色鮮やかです。が、季節がら、ほとんどが根菜です。

前回と違う種類だけ選んで紹介していきますが、まずはこちらの日野菜です。蕪の一種で、滋賀県の伝統野菜の一つ。室町時代に栽培が始まったという、歴史の長い野菜なんです。首もとの紫色がとてもきれいです。

次は、このとおり私の手のひらにでも、五個乗っかる大きさのCRもちばなというこ蕪。蕪は火をいれて、中がとろっとしたのが好きなので、これは糠漬けでなくて蒸し野菜にしようと思います。

この根から茎がにょこにょこ出ている野菜コールラビは、時々見かけますよね。これもミニサイズなので、直径は5センチ位しかありません。あまり使ったことないので、これはまず糠漬けにしましょう。

次のこれ、写真だけで何かわかる方おいででしょうか? 私、わかりませんでした😳 あの、ボルシチに使うビーツだそうです。確かに水煮とか料理されたものしか、今まで見たことなかったですねぇ。

最後のこちらは、紅芯大根。外観は大根らしく、首がうす緑で胴体が白ですが、切って見るとこのとおり、きれいな紅色が出てきます。とてもきれいなので、これはサラダにしましょう😊
予想以上に、毎回多種類のミニ野菜が届き、楽しいしとても勉強になります。
さて、昨晩はまた、糠漬け用のミニ野菜が、いっぱい届きましたよ。きれいでかわいいです😃

今年の気候は根菜類に適しているそうで、収穫は上々だそうです。9種類も入ってきた中味は、このとおりとても色鮮やかです。が、季節がら、ほとんどが根菜です。

前回と違う種類だけ選んで紹介していきますが、まずはこちらの日野菜です。蕪の一種で、滋賀県の伝統野菜の一つ。室町時代に栽培が始まったという、歴史の長い野菜なんです。首もとの紫色がとてもきれいです。

次は、このとおり私の手のひらにでも、五個乗っかる大きさのCRもちばなというこ蕪。蕪は火をいれて、中がとろっとしたのが好きなので、これは糠漬けでなくて蒸し野菜にしようと思います。

この根から茎がにょこにょこ出ている野菜コールラビは、時々見かけますよね。これもミニサイズなので、直径は5センチ位しかありません。あまり使ったことないので、これはまず糠漬けにしましょう。

次のこれ、写真だけで何かわかる方おいででしょうか? 私、わかりませんでした😳 あの、ボルシチに使うビーツだそうです。確かに水煮とか料理されたものしか、今まで見たことなかったですねぇ。

最後のこちらは、紅芯大根。外観は大根らしく、首がうす緑で胴体が白ですが、切って見るとこのとおり、きれいな紅色が出てきます。とてもきれいなので、これはサラダにしましょう😊
予想以上に、毎回多種類のミニ野菜が届き、楽しいしとても勉強になります。
| 11/26 | |
初冬の諸々ショット。 |
こんばんは。今日はまた、家から一歩も出ずに過ごしました。もっともその分、宅配は3つ受け取りましたけどね。
本日記事は、撮りためたアルバムから季節感のあるものをランダムにまいります。

三連休あたりから、人通りの多い場所にクリスマスツリーが、目立つようになりました。都内のある駅前広場でも、屋外のツリーの灯りに気持ちが高揚します。

季節限定の食べ物もいろいろですが、牡蠣好きの私にどうしても目に付くのは、このライン☺️ 珍しい牡蠣のつけ汁でいただくお蕎麦。蕎麦とうどんを選べたのだけれど、この場合はうどんが正解だったかな🤔

場所変わって、先週の京都駅前です。すっきりとライトアップされた京都タワーが、夜空にとても良く映えます。なんか、いつもより大きくみえます。

私の滞在場所は九条方面なので、東寺の五重塔が良く見えます。空気の澄んだ日は、夕映えがとっても美しいです。

ラスカルの季節イラストも、落ち葉炊きですね。因みに私、幼児の頃おちばたきを掃除するはたきが落ちたものだと思ってましたぁ😁
皆さんも、意味を取り違えて覚えていた言葉、ありませんか?
本日記事は、撮りためたアルバムから季節感のあるものをランダムにまいります。

三連休あたりから、人通りの多い場所にクリスマスツリーが、目立つようになりました。都内のある駅前広場でも、屋外のツリーの灯りに気持ちが高揚します。

季節限定の食べ物もいろいろですが、牡蠣好きの私にどうしても目に付くのは、このライン☺️ 珍しい牡蠣のつけ汁でいただくお蕎麦。蕎麦とうどんを選べたのだけれど、この場合はうどんが正解だったかな🤔

場所変わって、先週の京都駅前です。すっきりとライトアップされた京都タワーが、夜空にとても良く映えます。なんか、いつもより大きくみえます。

私の滞在場所は九条方面なので、東寺の五重塔が良く見えます。空気の澄んだ日は、夕映えがとっても美しいです。

ラスカルの季節イラストも、落ち葉炊きですね。因みに私、幼児の頃おちばたきを掃除するはたきが落ちたものだと思ってましたぁ😁
皆さんも、意味を取り違えて覚えていた言葉、ありませんか?
| 11/25 | |
ゆこう、ご存知ですか? |
こんばんは。小雨模様の東京ですが、寒くなったのであちこちの建物で暖房を効かせるようになり、のどがすぐ渇れてしまいます。消毒スプレーと一緒に、喉にシュッシュッするスプレーが外出には必要ですわ😲
さて皆さま、ゆこうという果物をご存知ですか?

一見普通のみかんのようですが、こちらが柚香(ゆこう)です。たくさん送られて来たので、早速先日作った竹籠に盛って悦にいってます😊 自然交配でできた、柚子の変種とのことですが、私も初めてお目にかかりました。

柚香は徳島県でしか栽培していないそうですが、この果汁で作ったぽんず醤油が絶品とのこと。今回は、仕込み材料のお醤油・みりん・鰹ぶし、全てを徳島県産で揃えてぽんず醤油づくりにチャレンジです。

最初の作業は、柚香の果汁絞りです。レモンより少し力が要る程度ですが、ともかく最初の写真の量の実をほとんど絞り切るので、根気がいります。が、実はこの後の工程は、笑っちゃう位簡単でした。まずジップロックに削りぶしを投入。

そこに柚香果汁と、それと同量の醤油を投入。次いで、果汁の1~2割のみりんを投入。みりんの量は、その時の柚香の甘さによって調節します。

以上4材料を入れたら、ジップロックの上から軽くモミモミするだけ。そのまま冷蔵庫で3日位寝かせておきます。
4日目に全体を濾したら、もうゆこうぽんず醤油の出来上がりです。因みにぽんずという単語は、オランダ語の果汁にあたるので、ポン酢というお酢は存在しないんですよ😲
さて皆さま、ゆこうという果物をご存知ですか?

一見普通のみかんのようですが、こちらが柚香(ゆこう)です。たくさん送られて来たので、早速先日作った竹籠に盛って悦にいってます😊 自然交配でできた、柚子の変種とのことですが、私も初めてお目にかかりました。

柚香は徳島県でしか栽培していないそうですが、この果汁で作ったぽんず醤油が絶品とのこと。今回は、仕込み材料のお醤油・みりん・鰹ぶし、全てを徳島県産で揃えてぽんず醤油づくりにチャレンジです。

最初の作業は、柚香の果汁絞りです。レモンより少し力が要る程度ですが、ともかく最初の写真の量の実をほとんど絞り切るので、根気がいります。が、実はこの後の工程は、笑っちゃう位簡単でした。まずジップロックに削りぶしを投入。

そこに柚香果汁と、それと同量の醤油を投入。次いで、果汁の1~2割のみりんを投入。みりんの量は、その時の柚香の甘さによって調節します。

以上4材料を入れたら、ジップロックの上から軽くモミモミするだけ。そのまま冷蔵庫で3日位寝かせておきます。
4日目に全体を濾したら、もうゆこうぽんず醤油の出来上がりです。因みにぽんずという単語は、オランダ語の果汁にあたるので、ポン酢というお酢は存在しないんですよ😲
| 11/24 | |
オンラインで南伊豆体験、その2。 |
こんばんは。今日は移動日で東京に戻りました。雨がぱらついて、少し肌寒くて、とても11月らしい気候の日でしたね。
さて、予告どおり昨日南伊豆と繋いだオンラインからの情報を、いくつか紹介しますね。

個人的に南伊豆=石廊崎と、尖った岬のイメージが強かったのですが、昨日のスライドではこんな地中海かと見まがうような海岸が紹介され、一挙にイメージが一新されてしまいました。

昨日のドリアにたっぷり入っていた伊勢海老。漁に出るのは未明の朝4時半頃だそうです。今でも未明の気温はかなり低いですから、船上でしっかり動けるよう、先に焚き火でよく暖まっておくそうです。

魚介の宝庫で、美味しいものも数えたらキリがないですが、スライドのなかで珍しかったのが、左側の写真のサンマの姿寿司。食べ応えありそう😋 右のかくれウナギは、ウナギが二段になっていて、ご飯の中からもう一枚出てくる豪華版です。

NHKの番組で、伊豆半島は太古に火山島が次々にぶつかってできた、と習いました。なので、温泉で有名な場所がたくさんありますよね。

そして、その温泉からの熱の利用にも、早くから目をつけていました。例えば、このようなマスクメロンの温室。ずいぶん前ですが、静岡のお土産にメロンをいただき、なんとなく静岡とは結びつかなかったのですが、温泉がカギでしたね。
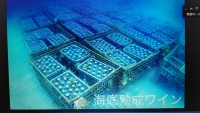
さて、こちらの珍しい写真は難破船の荷物ではありませんよ。最近時々耳にする、海底に沈めて熟成中のワインたちです。日光の影響を受けないので、劣化しないまま波の振動で熟成が早く進む、と言われていますね。

別の場所の海底ワインを一口飲んだことがありまして、穏やかな口当たりではありました。が、普通に熟成させた同じワインと飲み比べてみないと、はっきりとした違いは表現できないです。いずれにしろ、付加価値としてはとても面白いです。
南伊豆2月には、河津桜が満開になります。その頃旅行自粛になっていないとよいのですが。。。
さて、予告どおり昨日南伊豆と繋いだオンラインからの情報を、いくつか紹介しますね。

個人的に南伊豆=石廊崎と、尖った岬のイメージが強かったのですが、昨日のスライドではこんな地中海かと見まがうような海岸が紹介され、一挙にイメージが一新されてしまいました。

昨日のドリアにたっぷり入っていた伊勢海老。漁に出るのは未明の朝4時半頃だそうです。今でも未明の気温はかなり低いですから、船上でしっかり動けるよう、先に焚き火でよく暖まっておくそうです。

魚介の宝庫で、美味しいものも数えたらキリがないですが、スライドのなかで珍しかったのが、左側の写真のサンマの姿寿司。食べ応えありそう😋 右のかくれウナギは、ウナギが二段になっていて、ご飯の中からもう一枚出てくる豪華版です。

NHKの番組で、伊豆半島は太古に火山島が次々にぶつかってできた、と習いました。なので、温泉で有名な場所がたくさんありますよね。

そして、その温泉からの熱の利用にも、早くから目をつけていました。例えば、このようなマスクメロンの温室。ずいぶん前ですが、静岡のお土産にメロンをいただき、なんとなく静岡とは結びつかなかったのですが、温泉がカギでしたね。
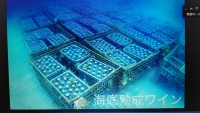
さて、こちらの珍しい写真は難破船の荷物ではありませんよ。最近時々耳にする、海底に沈めて熟成中のワインたちです。日光の影響を受けないので、劣化しないまま波の振動で熟成が早く進む、と言われていますね。

別の場所の海底ワインを一口飲んだことがありまして、穏やかな口当たりではありました。が、普通に熟成させた同じワインと飲み比べてみないと、はっきりとした違いは表現できないです。いずれにしろ、付加価値としてはとても面白いです。
南伊豆2月には、河津桜が満開になります。その頃旅行自粛になっていないとよいのですが。。。
| 11/23 | |
オンラインで南伊豆体験、その1。 |
こんばんは。今日は私一歩も外へ出ないで過ごしましたが、連休最終日でかなり人出あったのでしょうね。
さて、時々地方の食材を味わうオンラインに参加していますが、今日は南伊豆からのイベントでした。

昨晩届いた食材一式です。予想よりすごく充実していて、にんまりです。実は今回は、3月まで月に2回は食事会に参加していた、キッチハイクさんのイベントでした。

4月以降実際に集まるイベントは全て中止されていて、今日もオンライン。Zoomを繋げて開始までの待ち時間に、お腹が空いていたので、ばら摘み焼きのりをフライングしまいました。ちょうどよい塩気と磯の香りで、止まらない!

イベント開始間もなく、各自昨日送られた明日葉ビールを手にカンパーイ。明日葉は、たまに天ぷらでいただく位で、あまり馴染みのない野菜ですが、パンチがあるけど嫌みのない苦味で、油を使った料理によく合います。

一品目は、ブダイのエスカベッシュ。ブダイは伊勢海老漁の網に一緒にかかるそうですが、市場流通しないので地元でしか食べられません。素揚げしてからリンゴ酢に浸けてあります。とても身に弾力があって、食べ応えのある一品です。

二品目は、サザエとタコのアヒージョ。これまでいろいろなアヒージョ食べてきましたが、サザエ最高! 温めて食べる前提だったのですが、なるべく食材が固くならないよう、私は解凍しただけでいただきましたよ。

メインは、伊勢海老のドリア🤗 中は甘い伊勢海老がゴロゴロ状態で、とても贅沢で美味しかったです🥰 私はちょうどコロナ禍の広がる直前に、活伊勢海老を自分で捌いてお刺身にする経験をしましたが、あの時も南伊豆産でした。
食関連だけでも、様々なオンラインイベントがありますが、画像と同時進行で自宅で料理を作っていく形式は、バタバタして私はあまり楽しめないです。今日のように、調理済みのお料理が届いて、生産者さんのお話を聞きながらいただくのが、ベストですね。明日は、その南伊豆の情報を少しご紹介しますね。
さて、時々地方の食材を味わうオンラインに参加していますが、今日は南伊豆からのイベントでした。

昨晩届いた食材一式です。予想よりすごく充実していて、にんまりです。実は今回は、3月まで月に2回は食事会に参加していた、キッチハイクさんのイベントでした。

4月以降実際に集まるイベントは全て中止されていて、今日もオンライン。Zoomを繋げて開始までの待ち時間に、お腹が空いていたので、ばら摘み焼きのりをフライングしまいました。ちょうどよい塩気と磯の香りで、止まらない!

イベント開始間もなく、各自昨日送られた明日葉ビールを手にカンパーイ。明日葉は、たまに天ぷらでいただく位で、あまり馴染みのない野菜ですが、パンチがあるけど嫌みのない苦味で、油を使った料理によく合います。

一品目は、ブダイのエスカベッシュ。ブダイは伊勢海老漁の網に一緒にかかるそうですが、市場流通しないので地元でしか食べられません。素揚げしてからリンゴ酢に浸けてあります。とても身に弾力があって、食べ応えのある一品です。

二品目は、サザエとタコのアヒージョ。これまでいろいろなアヒージョ食べてきましたが、サザエ最高! 温めて食べる前提だったのですが、なるべく食材が固くならないよう、私は解凍しただけでいただきましたよ。

メインは、伊勢海老のドリア🤗 中は甘い伊勢海老がゴロゴロ状態で、とても贅沢で美味しかったです🥰 私はちょうどコロナ禍の広がる直前に、活伊勢海老を自分で捌いてお刺身にする経験をしましたが、あの時も南伊豆産でした。
食関連だけでも、様々なオンラインイベントがありますが、画像と同時進行で自宅で料理を作っていく形式は、バタバタして私はあまり楽しめないです。今日のように、調理済みのお料理が届いて、生産者さんのお話を聞きながらいただくのが、ベストですね。明日は、その南伊豆の情報を少しご紹介しますね。
| 11/22 | |
久しぶりの和菓子づくり、その2。 |
こんばんは。朝6℃でしたが、今18℃。上手く着るもの調整していかないといけませんね。
さて、昨日の続きいきますね。

二種類目も中は白餡。ここでは内に包み込む以外にも、少量確保しておきます。外側用の生地は桃色に染め、別途添え物用に黄色も用意します。

まず、いつもどおり桃色の外側生地で白餡を包みますが、完全に包み込む手前で、先ほど小分けした餡を蓋するように重ねます。ちょっとラディッシュみたいですね☺️

ここから、陶芸でお茶碗を作る感じで、内側を低くしていきます。外側の先端に、桃色と白がどのようにまじるか、で仕上がりの感じが大きく違ってきますよ。

じゃ~ん、これが以前から欲しかった、和菓子用の餡濾しです。これまで普通の茶漉しを使ってましたが、やっぱり網目が平らだと使い易いです。

見てのとおり、濾した生地はお花のしべになります。ずいぶんしべが大量だと思いますよね?はい、それには訳があります。

今回の椿は、花びらの下に空間を作り、しべは半分隠れます。なので、敢えてたくさん入れて花びらの隙間から見え隠れするようにしてあります。

花びらの仕上げは、昨日の三角木べらのVの辺で線をつけながら、内側へ押していきます。とても楽しい作業です。
最後に並べて、ツーショット写真です。
さて、昨日の続きいきますね。

二種類目も中は白餡。ここでは内に包み込む以外にも、少量確保しておきます。外側用の生地は桃色に染め、別途添え物用に黄色も用意します。

まず、いつもどおり桃色の外側生地で白餡を包みますが、完全に包み込む手前で、先ほど小分けした餡を蓋するように重ねます。ちょっとラディッシュみたいですね☺️

ここから、陶芸でお茶碗を作る感じで、内側を低くしていきます。外側の先端に、桃色と白がどのようにまじるか、で仕上がりの感じが大きく違ってきますよ。

じゃ~ん、これが以前から欲しかった、和菓子用の餡濾しです。これまで普通の茶漉しを使ってましたが、やっぱり網目が平らだと使い易いです。

見てのとおり、濾した生地はお花のしべになります。ずいぶんしべが大量だと思いますよね?はい、それには訳があります。

今回の椿は、花びらの下に空間を作り、しべは半分隠れます。なので、敢えてたくさん入れて花びらの隙間から見え隠れするようにしてあります。

花びらの仕上げは、昨日の三角木べらのVの辺で線をつけながら、内側へ押していきます。とても楽しい作業です。
最後に並べて、ツーショット写真です。
| 11/21 | |
久しぶりの和菓子作り、その1。 |
こんばんは。やっとGotoトラベル・イートの見直しが発表されました。止めるのは新規予約だけみたいですが、既に予約しているのはそのままでよいのすかねぇ?
さて、今日は和菓子作り用の道具を二つ入手したので、早速いくつか作ってみました。

一つ目はこの三角柱型の木ベラです。三つの角辺のうち、写真のように一ヶ所が浅いV字になっていて、ここを使うと生地に、細い二本線が引けます。

さて、お菓子の一種類目です。中に入れる餡は白餡。外側はダイダイ色をメインに、少量の黄色を用意して、この季節にどんぴしゃりの植物を作っていきます。

まず、ダイダイを平たい円形に潰したところへ、黄色をのせて一部をグラデーションに。このグラデーションを外側にして、白餡を包み込みます。

少し高さを潰してから、先ほどの木ベラで深めの筋を4本入れていきます。この状態だと、飾り細工をしたニンジンみたいですね😅

目指しているのはもみじ葉なので、さっきつけた筋と筋の間を摘まんで尖らせ、更に葉脈の細い筋を足します。私は作りながら、もみじ饅頭が頭にあったので、かなりふくよかな葉になりました😁

仕上げに木ベラのVの辺で、周囲に浅い短い筋をいれていきます。が、写真だとよくわからないかな😳
もう一種類、明日紹介するお菓子は、だいぶ難易度があがります。
さて、今日は和菓子作り用の道具を二つ入手したので、早速いくつか作ってみました。

一つ目はこの三角柱型の木ベラです。三つの角辺のうち、写真のように一ヶ所が浅いV字になっていて、ここを使うと生地に、細い二本線が引けます。

さて、お菓子の一種類目です。中に入れる餡は白餡。外側はダイダイ色をメインに、少量の黄色を用意して、この季節にどんぴしゃりの植物を作っていきます。

まず、ダイダイを平たい円形に潰したところへ、黄色をのせて一部をグラデーションに。このグラデーションを外側にして、白餡を包み込みます。

少し高さを潰してから、先ほどの木ベラで深めの筋を4本入れていきます。この状態だと、飾り細工をしたニンジンみたいですね😅

目指しているのはもみじ葉なので、さっきつけた筋と筋の間を摘まんで尖らせ、更に葉脈の細い筋を足します。私は作りながら、もみじ饅頭が頭にあったので、かなりふくよかな葉になりました😁

仕上げに木ベラのVの辺で、周囲に浅い短い筋をいれていきます。が、写真だとよくわからないかな😳
もう一種類、明日紹介するお菓子は、だいぶ難易度があがります。


